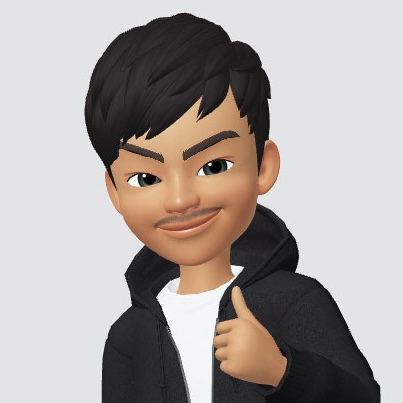情報の伝達およびコミュニケーションは、話し手と聞き手の双方が意識を向け合うことで、クオリティの高い意思の疎通や相互理解を生み出すことができます。
話す側には、発信の内容や意図を正確に伝えるための工夫が必要とされますが、聞く側にもまた、相手の意図を的確に汲み取る能力や、話の本質を理解しようとする姿勢が欠かせません。
『伝え方』と『解釈の仕方』の両方が、高い水準で機能してこそ、スムーズかつ的確なやり取りが成立するのだと思います。
ところが現代社会を見渡すと、こうしたバランスが著しく損なわれているのが現実です。
話がうまく伝わらないとき、その原因の大半は話し手の『言い方』や『言葉の選び方』などにあるとされ、聞き手の『解釈の仕方』に焦点が当てられることは、何故かほとんどありません。
特に最近では、聞き手が話の文脈や意図を汲み取ろうとせず、表面的な言葉じりだけを捉えた、極めて『低コンテクスト』な解釈をする人も増えているように思います。
話し手の至らなさばかりが強調され、聞き手の理解力の乏しさや解釈の仕方、洞察力の欠如などが論点となることはあまりない現状に、私は強い疑問を抱いています。
むしろ私は『話し手』よりも、『聞き手』の物事の捉え方に問題があることの方が多いと感じています。
相手が何を伝えようとしているのかを汲み取ろうとし、的確に物事を捉えられる人は、相手の言葉を断片的に切り取ったり、理解の不十分な状態で反論することはありません。
理解が浅い、または難しいと感じたときには、追加の情報や説明を求めるのが当然ですが、それをせず『相手に非を押し付ける』というのは、聞き手の理解や洞察が足りていないということの表れだと私は思っています。
さらに現代社会において、私がもう一つ問題視しているのは『歪んだ解釈』の広がりです。
話し手がまったく意図していないことを、聞き手の勝手な推測や憶測で解釈し、本質とはズレた捉え方をする人を、私はたくさん見てきました。
とりわけ今の日本では『察する文化』のデメリットが曲解を生み、ネガティブな受け止め方をしてしまう人が多く存在することに、深い懸念を抱いています。
また、議論や意見交換の場で何かを問いかけられた時に、詰問を受けているという捉え方をする人もしばしば見受けられます。(反省会をしている訳ではないんですけどね)
本来であれば、その時点での『事実』を述べ、それに基づいた今後の指針や対策を話せば良いだけのことなのに、それまでの自分の行いを正当化しようとして、言い訳じみた発言になる。(聞いてもいないことや論点のズレた発言をして、相手を不快にさせる)
こちらも『解釈の歪み』の典型例であり、責められているかのような『誤った受け止め方』をしないよう、聞き手は注意する必要があるでしょう。
その場に適した発言や、しっかりとした会話のキャッチボールをするためには、ピントの合った解釈が欠かせませんからね。
さいごに
解釈の不足と解釈の歪み。
こうした課題に対する理解を深め、解釈の力を高めていくことが、質の高い情報の伝達やコミュニケーションを築き上げるための重要なポイントだと思います。
もちろん、話し手に問題がある場合もありますので、すべてを聞き手の理解の偏りとして扱うつもりはありません。
ただ、どちらの立場にしても、互いが「どう受け止められるか」を意識し合わなければ、真の意味での理解は生まれません。
このことはまさに、この記事の本質でもありますので、意図を的確に汲み取り、より良い解釈へとつなげていただけたら嬉しく思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※この記事は、私自身の思考や考察をもとに、A Iのサポートを受けて文章を推敲しています。