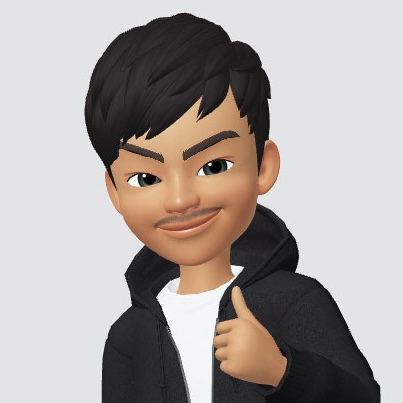本日は、十月最初の日曜日。
今年もフランス・パリロンシャン競馬場では、長い歴史と伝統を誇る「凱旋門賞」が行われました。
このレースは日本でも、地上波で毎年のように中継されており、多くの競馬ファンからも高い注目を集めています。
今回、日本からは三頭の馬が挑戦しましたが、最高順位は「ビザンチンドリーム」号の五着。
残念ながら今年も、日本調教馬による悲願達成とはなりませんでした。
このレースが世界でも、屈指の格式を誇る舞台であることに間違いはないのですが、競走の質そのものが日本の競馬とは大きく異なるため、日本の調教馬がこの競争で本来の力を発揮するのは簡単なことではありません。
なかでも最大の違いは「馬場」にありますが、日本の芝は乾いて硬く、スピード勝負に適した軽い馬場であるのに対し、パリロンシャンの芝は水分を多く含んだ重い馬場で、まるで田んぼのようだと表現されるほどの走りづらさがあることも、特徴のひとつです。
こうした馬場では、地面からの反発力も弱いので、日本の競馬ではよく見られる「鋭い末脚」が不発に終わることも、少なくありません。
現地入りのタイミングを早め、環境への順応を図ることもひとつの策ではありますが、芝の質や地形そのものが根本的に異なる以上、短期間での適応には限界があると思います。
もし私がオーナーだったとしたら、競争環境が大きく異なる海外のレースを積極的に狙うということは、あまりしないでしょう。
仮にフランスでの栄冠を目指すのであれば、所有馬を日本ではなくフランスで育成し、現地の競馬に順応した状態で挑んだほうが良いと思います。
その方がより現実的ですし、本来の力を発揮するのが難しい状態で勝負をすることに、あまり意義を感じません。(戦うのは自分ではなく馬ですから)
能力が高いこと(強い馬であること)も大事ですが、それ以上に、現地の競馬や環境に適応できるかどうかの方が、さらに重要な気もしています。
もちろん「日本調教馬による凱旋門賞制覇」という夢には、計り知れないロマンがあります。
しかし、日本の競馬では圧倒的な強さを見せるサラブレッドたちが、異国の地で本来の力を出し切れずに敗れていく姿を見ると、何ともいえない気持ちにもなります。
「挑戦することに意味がある(意義がある)」とはよく言いますが、勝負や競争の観点から言えば、私は必ずしもそうとは思いません。
むしろ、自らが最も輝ける舞台で確かな結果を残すことのほうが、より大きな価値があるのではないかと感じています。
秋の天皇賞、ジャパンカップ、そして年末の有馬記念。
馴染みのある環境で、自分の持てる力を存分に発揮することが、馬にとっても、そして応援する側にとっても、最も健全で意味のある挑戦なのではないか。
ここ数年の凱旋門賞を見て、私はそんな考えに落ち着いています。
P.S.
帰宅途中には、思わぬハプニングがありました。
乗車していた田園都市線が運転を見合わせ。(ちなみに終電)
当初は「車両点検」とのことでしたが、その後の追加情報では、「車両同士の衝突事故」であることが明らかになりました。
さらには脱線も発生しているようで、警察による現場検証が延々と続いており、電車は動く気配を見せません。(この日記も、停車中の電車の中で書いています)
家に着くのは一体何時になるのでしょうか…